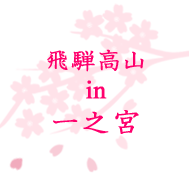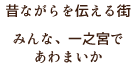|
|
|
|
|
|
|

宮笠の歴史
宮笠の歴史について記した古い文献としては、飛騨の文人・津野滄洲(1718-1790)が天明3年(1783)に著した「飛州産物狂歌集」があります。
ここでは、飛騨各地の名物等を狂歌として歌っており、当時飛騨の名物として知られていた「一宮檜笠」として、次のように紹介されています。
「松の葉の 雨もらさぬは 唐のこと 檜は 日本一の 宮笠」
前者は、代官である長谷川忠崇が1730年頃の様子を取りまとめたものを、1892年に刊行しており、前述の「飛州産物狂歌集」より古い時代のことが記録されていると思われますが、その中には宮笠に関する記述はありません。

一方、明治に入って1873年に富田禮彦が著した「斐太後風土記」には、当時に宮村の産物として「檜笠千二百蓋、赤檮(いちい)笠」と書かれています。周辺の村では産物として笠が記載されていないことから、当時から宮村の特産品であったことが読み取れます。
また、1925年、大野郡宮村教育会によって発行された「宮村紀要」には、宮笠の起源について次のように紹介されています。
「笠の生産は古く徳川時代に始まり、口碑によると今より二百五十余年前、天和二年(1682)八月、美濃国郡上郡より伝授を受けたといい、爾来問坂部落において多くこれが製造に従事している。」
この記述によると、笠を編む技術は、今から約330年前に一之宮町に伝えられたということになります。現在、高山市の無形文化財に指定されて今に至っていますが、後継者の確保が急務となっています。

宮笠の材料
宮笠の主な材料は、ヒノキやイチイからつくる「笠ひで」と、竹から作る「骨竹」「縁竹」「緒たて竹」です。
作り方は、直径30~40㎝になるヒノキを伐採して2尺(約60㎝)に玉切りし、機械にかけて大根のかつらむきの要領で薄板を取り、約6㎜幅に裁断して作ります。
ヒノキの笠ひでは、ヒノキ材が入手しやすく加工も容易なことから、大量に生産できるという長所があります。
イチイは位山にまつわる言い伝えや、平治元年から続く天皇家への笏木献上など、歴史的に一之宮とつながりの深い樹木です。

宮笠に用いるイチイ材は、位山など一之宮で伐採されたイチイを用いていますが、最近では位山のイチイ材が入手しにくくなっています。
また、材が硬いことから機械にかける際に一昼夜煮て柔らかくしなければならないことや、微小な節の痕が多く使えない部分が多いことなど、貴重な材料といえます。
保存状態が良ければ、年月を経るにつれて深みのある茶色に落ち着いて、ツヤが出てきます。
竹は、一之宮町で竹の良材が得られないため、下呂市萩原町周辺飛騨川沿いの竹(モウソウチク)を用いています。
傷みやすい辻を補強するために、セミ笠などにはカンバ(やまざくら)の樹皮をさします。
また紅白などには、カンバの色に染めた笠ひでをさして補強します。
宮笠の種類
主に生活の道具として使われた宮笠には、用途などによってさまざまな種類があります。
その種類は、次のようなわけ方により分類できます。


|
①材料によるわけ方 |
②寸法によるわけ方 |
|
笠を編む材料には、白っぽい色をしたヒノキ、または赤茶色のイチイから作った笠ひでを用います。 |
寸法によるわけ方として、笠の半径を表した呼び名で、「6寸5分」「7寸」「7寸5分」「8寸」などがあります。 |


|
③形によるわけ方 |
④編み方によるわけ方 |
|
紅白など普通の笠ひでで編んだ笠はとがった形をしていますが、「しんこき」という作業工程で笠ひでの中央部を細く加工することで、 |
笠ひでを編む場合、編み目の単位を「あや」といいます。基本は交差する笠ひでを3枚飛ばして編み込んでいく方法で、「3枚あや」とも呼びます。 |

宮笠の使用
工芸品としても価値あるセミ笠などは、装飾品として玄関や室内に飾られることもありますが、飛騨では実用品として、農業など野外作業や近所への外出時に宮笠をかぶる人を良く見かけます。
また、鮎釣りなどの釣り人にも笠をかぶる人を見かけます。
さまざまな帽子が売られている現在ですが、宮笠には、他のかぶりものに比べて、「軽い」ことや「通気性が良い」こと、そして「少々の雨なら防いでくれる」などの長所があります。
これらの長所は、ヒノキなどの笠ひでを使うことによるもので、乾燥しているときは軽く、編み目のすき間が通気を確保してくれます。雨などで濡れると、水分を含んだ笠ひでがぼうちょうしてすき間をふさぐため、雨水は表面を流れます。
昭和40年頃には年間生産量5万5千蓋を誇った宮笠ですが、近年は3千蓋程度となっていますが、木という素材の特徴を十分に生かした、生活に根差した実用の道具だからこそ今なお愛用者がいるのでしょう。